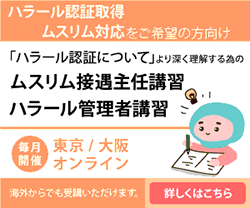日本ハラール協会は、JAKIM(マレーシア)、MUIS(シンガポール)、BPJPH(インドネシア)、HAK(トルコ)及びGAC(湾岸諸国)とMOIAT(UAE)から承認・認定されたハラール認証団体です。
Mega Halal Bangkok, Purity way of Life
活動報告
イベント名: Mega Halal Bangkok, Purity way of Life
主催: CICOT(Central Islamic Council of Thailand –タイ中央イスラーム評議会)
目的: CICOT MRA調印式出席
場所: BITEC バンコク タイ

タイ王国とムスリム
タイ王国は仏教国でありながら、国民の10%をムスリムが占める。多くは、マレーシアとの国境付近や南の方に在住しており、過去にはムスリム人口が30%を占めるプーケット島にてCICOT主催のイベントが開催されたこともある。
数字でみると決して多くはない印象のムスリムであるが、街中ではちらほら見かけ、例えば10件ある屋台のうち1件がムスリムのハラール屋台というイメージである。それでも一般的な飲食店のほとんどは豚肉を扱う店なので、食事時に私が座れる店を探すのは容易でない。グーグルマップで検索、タクシーで20分ほど行ってようやくハラールレストランが数件見つかる、という具合である。余談ではあるが、東南アジアで利用頻度が高いGrabなどの配車サービスはここバンコクでも低価格で利用でき、渋滞に巻き込まれさえしなければ非常に便利である。また電車も簡便で、今回もホテルと会場の往復に問題なく利用できた。30年近く前に訪れた際は電車などなく、街並みも今ほど洗練されていなかったバンコクだが、当時の「洋服も食べ物もすべて屋台で揃う」という点や、活気ある古き良き東南アジアの雰囲気は今なお健在だった。
Central Islamic Committee of Thailand(CICOT)
さて、この10%のタイ・ムスリムのコミュニティーの柱として存在するのがCICOTというNGOである。CICOTはハラール認証のほか、全国におけるモスク、イスラーム教育、冠婚葬祭など、ムスリムの生活にかかわる各要素の取りまとめをするほか、「Sheikhful Islam」という部門が各地におけるイスラーム学者の代表を取りまとめ、海外から要人が来訪した際の接遇をタイ国家からの用命で執り行っていた。

タイとのハラール相互承認を更新
CICOTの機能のひとつに、国内におけるハラール生産品や飲食店等に対するハラール認証の付与・管理がある。同国では昨今、国内で製造するハラール認証品の使用原料はハラール認証の取得が条件となり、2018年には世界の各認証団体に対し、CICOTとの相互承認の要求を開始した。今回の弊会の訪問の目的は、相互承認が開始されて以降初めての「更新承認」であった。
弊会ではこの更新承認のため、今年の2月頃から必要書類を提出し、それらを基に精査がなされるのを待っていたが、CICOTからは特に是正要求や現地査察などの要求も無く、某国の認証機関のように認証範囲にカテゴリーを設けたわけでもなければ、監査員に対する具体的な経験年数やカテゴリー別の資格要求をすることもなく、比較的容易に審査が終了した。そのためか、他の国との相互承認式では見かけないような新しい認証団体の顔ぶれを見かけた。
日本からも認証団体が数社参加していたが、いずれも無事に更新承認を取得することができた。


ノンムスリム国家とハラール産業
タイ国は仏教国である反面、自国の強みである食品製造を世界へ拡大するツールとして、ハラール認証を以前から利用してきた経緯がある。国家がCICOTのハラール施策に予算を付与することから、製造業者がハラール認証を取得しやすい環境にあり、世界各国に対するタイ・ハラールの認知キャンペーン活動も行われている。
会議2日目の冒頭、前首相がスピーチをされた。在任中のエピソードとして、自国の輸出拡大のためにハラール認証が不可欠であることを認識し、国家予算の増額を行い、その後押しに邁進したという内容のお話であった。
アメリカに20%の関税をかけられた今、同じような製品を製造する隣国ベトナムに価格面でどう勝てようか。他方、中東やアフリカに目を向けると、人口の爆発的増加、特にムスリム人口の増加には無視できない勢いがある。これを市場に取り込むためにはハラール認証が不可欠である・・という判断の下、同国では従来からハラール産業を全力でサポートする取り組みが行われ、その結果、現在タイから輸出される製品の40%がハラール認証を取得し、輸出額を順調に伸ばす一因となっている。仏教国でありながらも食品製造業が自国の強みであると自認し、国家戦略としてハラール産業に取り組んだ結果である。
「まずは自国の強みが何かを把握する必要がある。そのうえで、それをどう活かせるのかを考える」
国益追求のために自国の強みを最大限に活かすべく、先見的にハラール産業に取り組むことを選択したタイは、同じくノンムスリム国家である日本のような国がハラール産業に取り組む際の模範例になるといえそうだ。
日本のハラール産業の特徴は「食品、化粧品、医薬品におけるハラール原材料の供給」であり、我々の認証取得企業も、多くがこれらを供給する原料メーカーである。タイが得意な消費者向け商品とは対照的に、日本では製品を構成する食品素材をはじめ、添加物、加工助剤といった化学・生化学品が得意分野で、輸出されるハラール認証品の多くを占めている。このような得意分野を可視化し、いったい毎年どれくらいの規模・金額のハラール認証商品が輸出されているのかを把握すれば、日本の強みが何であるかが一目瞭然となるだろう。
CICOTに話が戻ると、NGOでありながらも国が支援するに値する「国益」を生んでいる点が注目される。タイ人によるタイ国への寄与である故、外国人による寄与ほどではないものの、「イスラーム教徒」という仏教国の中では特異な存在による寄与、という点に着目したい。
同国においても仏教徒によるイスラーム教徒への差別は存在し、行政によって一部のムスリム地域が弾圧されることもある。しかし、それ以上にムスリムの活動が国に対してポジティブに影響し、国益をもたらすと理解されたため、国家を挙げてのハラール政策に繋がったわけである。
同様に、日本におけるハラール産業への取り組みにおいても、一見異質なものが日本の国益に寄与できる可能性に気付くことにより、事業者が得る直接的な利益だけではなく、日本の雇用創出、産業活性化、税収入などにつながる可能性を秘めていると言えよう。
逆に我々の側としては、認証団体が得た利益をワカーフ(共済)として、国内在住のムスリムコミュニティのインフラ整備に活かすことが可能になり、共栄共存に繋がっていく。
昨今、日本では外国人やムスリムに対する排他的な言動等が散見される。それは一部の問題行動が日本の環境や民族性を損ねる等のマイナス要素として捉えられ、日本人が自国を守ろうとしている動きであろうと理解しているが、逆に外国人やムスリムが日本社会にポジティブな影響を与えるものと理解されれば、このような感情の増長を防げるかも知れないと考える。
我々はハラール産業の発展を「互いに協力しながらより良い社会を目指すことができる一つのツール」と捉え、今後も日本社会とムスリムコミュニティの両方に貢献できる活動に邁進したい。
レモン史視