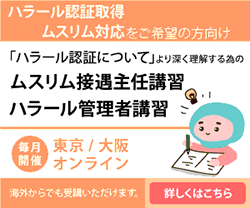日本のハラール促進のため、弊会にできることを、できるだけ
インバウンドツーリズムが加速する昨今、国内では大型の国際イベントが立て続けに予定されているなど、日本のインバウンド業界には明るい兆しが続いており、更に国内に就労・就学する外国人の増加、ムスリム世帯数の増加等も併せて、国内におけるハラール・ムスリム対応の需要は急速に拡大しています。
そんな中、「こんなところにムスリム対応があればいいな」と我々自身が普段から感じ、また弊会が長年温めてきた「ムスリムの暮らしに直結した分野に力を注ぎたい」という思いも含めて、国内のフードサービス事業者や小事業者が費用や利便性の面でハラール認証をより取得しやすくなるよう、弊会はこのたびフードサービス関連の認証制度を刷新しました。
1.【国内向け飲食料品ハラール認証サービスの種類】
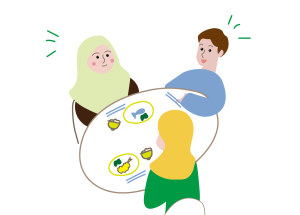
- ハラールフードサービス施設認証:
食事は完全にハラールで、アルコール飲料の提供がない店舗・施設・キッチン向けです。
対象施設例:
レストラン、カフェ、ホテルキッチン、キッチンカー、学校・施設などのカフェテリア、イベント会場における簡易キッチン、屋台等
- ムスリムフレンドリーフードサービス施設認証:
食事は完全にハラール、アルコール飲料の提供がある店舗向けです。上記ハラールレストラン認証との違いはアルコール飲料の提供がある点のみです。
対象施設例:
レストラン、カフェ、学校・施設などのカフェテリア等、ダイニングエリアを含むもの
- 国内向けハラール飲食品製造認証(小事業者のみ):
冷凍弁当、冷凍食品、肉加工品、パン、スイーツなど消費者向けの商品を製造する小規模の製造者向けです。国内消費の飲食品に限定されますので、輸出向けや、輸出向けの製品認証企業へ原料として納める場合、企業規模が大きい場合は除きます。
「ハラール認証基準 国内向け飲食料品 JHAS3001」は、海外認定・承認機関の要求事項に沿って海外輸出を目的とする「ハラール認証基準 製品JHAS1002」とは異なり、国内でムスリム対応をするにあたって、事業者も消費者も安心して取り組むことができる必要最低限の要求事項を納めたものです。

2.【認証取得までの流れ】
- 知識習得: イスラーム、ハラールについての基本情報、認証プロセス等をご理解頂きます。(「フードサービス施設及び、国内用ハラール飲食品製造中小事業者向け講習(毎月オンライン実施)」のご受講を推奨)
- 事前審査: 書類を確認し、認証取得の可能性を判断致します。
- 本申請: 事前審査で認証取得が可能であると判断された場合、本申請が可能となります。
- 書類監査: ご提出書類一覧表に基づき書類をご提出頂きます。
- 現地監査: 監査員が施設へ訪問し、監査を行います。
- 判定: 監査完了、判定にて承認後、認証書の発行
取り組みの経緯
日本ハラール協会は、元々は「国内の食に関するインフラを整えよう」というところから設立されました。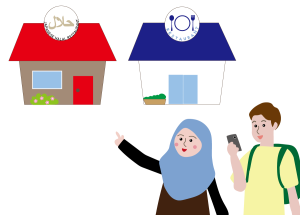
ところが2013年に「ハラール認証ブーム」の波が日本に押し寄せて以降、海外各国との相互承認をいち早く確立した弊会は、日本企業が海外輸出をするための認証監査に追われることとなり、経費、労力、時間のほとんどを海外承認・認定取得の方面に費やす結果になりました。
しかしながら、国内を振り返ると、未だにハラールレストランは少ない、ハラール食材の調達も少しは容易にはなったものの、まだまだ困難。海外からのお客さんも右往左往している・・・という状況が続いています。当初弊会が目的としていた国内の食に関するインフラ整備の部分が大きく後れを来していること、本来の目的を達成できていない現状を改めて実感する昨今でした。
そこで弊会は、既にある認証基準の原型をブラッシュアップし、使い勝手の良いものに改良する作業に取り掛かりました。しかし、ここで一番苦慮した点は、消費者が良しとすることが必ずしも事業者にとっても良いとは限らない点です。そのバランスをとりつつ、消費者にとって不安のない基準にしなければなりません。また、認証基準ですので、要求して答えが出る形、すなわち監査ができる形にしなければいけません。
外部メンバーにもアドバイスをもらいつつ、弊会内のエキスパート達と何度も何度も議論を繰り返し、2年以上の歳月と多くの方々の協力を経て、ようやくこの基準の完成に漕ぎつけたのでした。
こうして、飲食店をはじめとする、あらゆる業態のフードサービス施設、およびこれまでの認証基準では申請が困難であった国内販売・国内消費のみが対象の小規模のお土産製造業など、この認証基準を用いることで、多くの事業者様の認証取得の可能性が大きく広がります。
ところで、ハラール認証がなければムスリム対応をしたとは言えない?
そんなことはありません。ムスリムが知りたい内容を開示することで、それを見て利用するかしないかの判断を自身でしていただく方法があります。ピクトグラムなどで表現するほか、ハラール肉使用・不使用、アルコール飲料不使用、などわかりやすく表現し、判断材料として提供します。一方で、ハラール認証の最大のメリットは、一目で不安を解消するツールとして大変有効である点です。
弊会が提供するこの新認証は、まずはハラールを普及させ、そのメリットを最大限社会に還元することを目的としていることから、認証に係る費用は必要最低限に設定されています。
費用の例
小規模企業の場合:事前審査費用:50,000円、監査認証費用:100,000円~(税別)*交通費・宿泊費用別途 詳細はお問い合わせください。
自社の既存のビジネスに対し、ムスリム対応をしようと思うその理由を振り返ってみましょう。
1:既にムスリムの顧客が沢山来ているが、今後も増えてほしい。きちんと対応した形で顧客をお迎えしたい。
2:今はまだムスリムの顧客は利用されていないが、今後新たに呼び込みをしていきたい。
いずれの場合も、客足を増加させ、売り上げに繋げることが第一の目的になります。従って、ムスリム対応することはマーケティングの一環であることを念頭におき、その点においてムスリム対応を自社で取り入れるべきか、可能か否かを判断していきましょう。
売り上げを増やす目的なのですから、コストが掛かりすぎても問題ですし、今より手間が増えすぎても困ります。しかし、一方でマーケティングとして「ムスリム対応している」ことをアピールし、売りにするわけですから、顧客に納得頂ける内容でなければ意味を成しませんし、逆に不快感を与えてしまえば逆効果になってしまいます。
・フードサービス施設及び、国内用ハラール飲食品製造小事業者向け講習 で理解を深めてみましょう。
・講習を受講したが、その後どのように進めればよいのかわからない。→問い合わせフォームから面談を申請し、懸念点を解消してみましょう。
・社内にてムスリム対応をすることを決定した。→国内向け飲食料品ハラール認証申請へ進みましょう。
当協会の飲食店向けハラール認証には、ハラールフードサービス施設認証やムスリムフレンドリーフードサービス施設認証があります。
一方で、認証ではなく「情報開示」つまり、使用する食材や調味料に関する情報を開示することで利用者に選択肢を与える方法があります。飲食店の場合、直接利用者(消費者)と対話して情報を伝えることができるため、利用者が食べる、食べないの判断ができるよう情報開示することで十分な場合があります。「情報開示」は、特に個人店など個々の顧客対応ができる店には有効な手段といえるでしょう。しかし、規模の大きな店舗やチェーン店の場合、個々の顧客へ必要な「情報開示」をすることが困難です。むしろ、ハラール性に関する情報を一目で理解できる内容を提示していれば簡単に情報を伝えることができ、この場合は、「ハラール認証」が有効だといえます。
また「ムスリムフレンドリー」という言葉は、いろいろな意味でつかわれる場合があり、注意が必要です。
一般的にムスリムが「ムスリムフレンドリー」と聞くと、食事に関しては「ハラール」であると理解をします。一方、日本では「メニューの一部だけハラール」とか「ムスリムのことを考えながら作りました」というような場合も「ムスリムフレンドリー」という言葉を使用するケースがあり、誤解を生む場合があります。
弊会のムスリムフレンドリーフードサービス施設認証は、「食事はハラールのみ」としています。なぜなら、非ハラール肉とハラール肉の両方を取り扱う飲食店で、限られたスペースで隔離・分離してハラール性の担保を確保することは難しいと考えるからです。
弊会の飲食店に対する認証の目的は「利用者が安心して利用できること」であります。もちろん提供者側の利用しやすさも大切です。
また、利用者自身によって許容できるハラール性のありかたも十人十色ですので、利用者と提供者の双方が安心してサービスを受ける・提供する環境の整備が、持続可能なサービスの提供に繋がります。そのため、最大のリスクである「ハラール性を損ねる」ことがないことに重点を置く必要があります。
これが双方の共通の認識であると理解し、その一番良い形が「ハラールなものだけを提供する」環境を作ることである、と考えます。少々時間、プロセス、労力がかかりますがサービスの基本である「安心・安全」を確保することができます。
新しい認証にご興味を抱かれた事業者さまは、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。